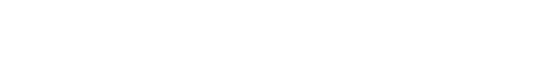Judges
審査員
ミハウ・ソブコヴィアク
ポーランドの音楽家の家庭に生まれる。10歳でテレビ番組「Akademia Muzyczna(アカデミア・ムジチナ)」に出演しピアニストとしてデビュー。その後、ポーランド国立フィルハーモニー・ホール等多くのコンサート・ホールで演奏し、海外の国際音楽祭にも多数参加する。作曲家、ジャズ・ピアニストとしても活躍。ワルシャワ・ショパン音楽院(現・ショパン音楽大学)ピアノ科卒業後、チューリッヒ音楽院研究科留学。アンジェイ・ヤシンスキ、イェジー・マルクウィンスキ、テレサ・マナステルスカ、ガブリエラ・ワイスの各氏に師事。1995年フランツ・リスト国際ピアノコンクール(ワルシャワ)入賞。1996年フレデリック・ショパン協会より奨学金を得る。1997年ヨーロッパ・ピアノフォーラム(ベルリン)に出演。2017年にリリースしたCD「Jazz Loves Chopin」はe-onkyo musicのTop 100 Albumランキングで1位を獲得。2018年公開の映画「羊と鋼の森」にピアニスト役として出演。2022年に開催された「ウクライナ人道支援チャリティー・コンサート」にて神奈川フィルハーモニー管弦楽団と演奏。2024年にかわさきジャズにてトリオバンド「Trivergents」として出演。現在、福島学院大学教授、昭和音楽大学講師。ピティナ、全日本ピアノコンクール、ショパン国際ピアノコンクール in ASIAの審査員、ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japanの審査員長。Japan Jazz Pop Piano Competitionの創立者、及び審査員長。

米国メリーランド州出身。
バージニア州シェナンドア大学にて学士、ニューヨーク州ニューヨーク市立大学ブルックリン校にて修士、オハイオ州クリーブランド インスティテュート オブ ミュージックにてコラボレーションピアニストとして、伴奏法やアンサンブルを学びプロフェッショナルスタディーズの学位を取得。
在学中、バルトーク・カバレフスキー国際コンクールで第 1 位、コンチェルトコンクールで優勝、ダリウス・ミヨー賞受賞。
コラボレーションピアニストとして演奏会を多数こなし賞賛を得る。オハイオ州アクロン大学、山口芸術短期大学での教鞭後、現在、米国ウエストバージニア州ザイオン エピスコパル教会にて音楽監督兼オルガニストに就任。

コチシュ・クリスティアン
1982年ハンガリーに生まれ、8歳よりピアノを始める。
2000年ハンガリー国立リスト音楽大学に入学、ピアノをドラフィ・カールマン氏、室内楽をビハリ・ラースロー氏に師事。
2006年同大学を最高点をもって卒業し、2008年より拠点を仙台に移す。 演奏活動の傍らカワイ音楽教育研究会主催講座の講師を東北6県の各都市に於いて務めるなど後進の指導にも力を注いでいる。

アガピエ・ドラゴス・クリスティアン
ルーマニアジョージユネスク芸術大学ピアノ科、同大学院修士科修了。
ヴェネチアにて、老舗カフェフローリアンオーケストラのメンバーに最年少で入団。レパートリー曲は300曲以上
フェニーチェ歌劇場でコルペティトールを6年間務め、2005年に日本にフローリアン楽団メンバーとして日本来日をしました。
2008年よりソロピアニストとして北海道から鹿児島まで全国規模で演奏を行っている。
カルティエVIPパーティー、レクサスクリスマスコンサート、テレビ朝日「関ジャニ∞のTheモーツァルト 音楽王NO.1決定戦」東海テレビ「日本のバイオリン王鈴木政吉物語(ピアニスト役)」出演。バイオリニストの古澤巌氏ツアー、テノール歌手のベー・チェチョル氏などコラボレーション
日野原重明氏メモリアルコンサートにて演奏
松田聖子さんMV 演奏出演(260万回以上再生)
2019年〜宗次ホール主催ソロリサイタル
2020年2月東京オペラシティーにてソロリサイタルを行い満員御礼の大盛況を収めた。
2022年 5月7月 俳優 プレミアムコンサート
愛知県芸術劇場・アクロス福岡円形ホール
俳優 上川一哉 ピアノ アガピエクリスティアン
2022年 35周年記念 国際親善交流特別演奏会
東京芸術劇場コンサートホール
2022年 10月 ルーマニア大使館主催
大使向けクローズドパーティーゲスト出演
2022年 11月 沖縄復帰50周年記念コンサート
ソロリサイタル 沖縄コンベンション劇場
2023年Netflix 映画 『IN LOVE AND DEEP WATER 』出演
などコンサートからメデイアまで多岐に渡り活躍中

エフゲニー・ザラフィアンツ
クロアチア国籍、ロシア・ノヴォシビルスク生まれのピアニスト。
音楽一家に育ち、6歳から父にピアノを学び、モスクワ音楽院附属中央音楽学校でエレナ・ホヴェンに師事。グネーシン音楽学校やグリンカ音楽院を首席で卒業し、数々のコンクールで入賞。1993年のポゴレリッチ国際コンクールで第2位となり、クロアチアに移住し、世界各国で演奏活動を展開。
日本には1997年から毎年複数回来日し、東京をはじめ全国でコンサートを行う。2004年、ロシア・フィルハーモニー管弦楽団との共演を皮切りに、チェコ・プラハ管弦楽団やザグレブ・フィルハーモニー管弦楽団とも共演。室内楽でも高く評価され、特にザグレブ弦楽四重奏団やチェコゾリスデンとの演奏は絶賛されている。
また、レコーディング活動も精力的に行い、日本ではALMレコードから約20枚のCDをリリース。ナクソスからもCDをリリースし、スクリャービンの前奏曲全集が『グラモフォン』の月間ベスト10に選ばれる。弱音の美しさとダイナミクスの幅広さが特徴とされる。ロシア、クロアチアで大学教授、愛知県立芸術大学教授、現在金城学院大学講師。日本在住。

カトヴィツェ音楽院(ポーランド)卒業、在学中はヨゼフ・ストンペルに師事。卒業後1991年~1996年にかけてカール・ハインツ・ケメリング、アンドレ・デュモルティエ、ジャン=クロード・ヴァンデン・エイデンのもとで研磨を積む。
ロン=ティボー国際コンクール(第2位、聴衆賞、ヨーロッパ参加者最高位受賞)、モントリオール国際音楽コンクール他で受賞。第12回ショパン国際ピアノコンクール(1990年ワルシャワ)では最も優れたポーランド人参加者に選ばれ、ポロネーズ賞を含む特別賞を受賞。
ソリスト・室内楽奏者として、欧州、北・南米各地にて演奏。ポーランドのほぼ全てのオーケストラと共演し、AUKSO室内管弦楽団、シレジア弦楽四重奏団、カメラータ弦楽四重奏団、王立弦楽四重奏団、シモン・クセソヴィエク(vn)、ピオトル・プラヴネル(vn)、エヴァ・イジコフスカ(sp)と共演。
録音も数多く、ポルスキ・ナグラニア、ベアルトン、DUX、ポーランド・ソニー・ミュージック、IMC、シャンドス各レーベルにて、バツェヴィチ、ブラームス、ショパン、ドビュッシー、リスト、シューマン、シマノフスキ、ザレンプスキの作品などを含む10枚以上の録音を発表している。ショパン研究所レーベルでは、1848年製プレイエルと1849年製エラールを用い録音を行った。2000年、2005年にはフレデリック・ショパン・グランプリ・ディスク大賞受賞、2002年、2009年、2019年にはフレデリック賞を受賞。
1998年より教育活動にも携わり、現在カトヴィツェ音楽院ピアノ科教授。2012年から2016年まで同音楽院ピアノ科主任。2020年から2023年までショパン音楽大学の教授も務めた。
これまでにロン=ティボー国際コンクール(2009)、ショパン国際ピアノコンクール(2015, 2021)、ホロヴィッツコンクール(キーウ 2016, 2019)、A.ルービンシュタインコンクール(北京 2016)、パデレフスキ国際ピアノコンクール(ビドゴシチ 2010, 2013)他、オーストラリア、ブルガリア、カナダ、フランス、日本、シンガポール、イタリア、アメリカにて多数のコンクール審査員を務める。また、ポーランド国内外にて定期的に公開講座や公開レッスンを開催。2023年、第2回ショパン国際ピリオド楽器コンクール審査委員長。2010年から2017年までカトヴィツェ国際ピアノマスタークラス主催。2014年よりショパン研究所企画委員。2021年12月より、ワルシャワ・ショパン協会理事。2025年、第19回ショパン国際ピアノコンクール審査員。


リヒャルト・フランク
スイス・チューリッヒで生まれる。チューリッヒ市立音楽大学に学び、ピアノ指導はイルマ・シャイヒェット夫人。スイス国立音楽教育連盟のピアノ教師ディプロマを取得後、 ドイツ国立フライブルグ音楽大学大学院卒業。ピアノ指導はエディット・ピヒト =アクセンフェルト教授。彼女のマスタークラスで将来の妻、真野英子と知り合いその後2人は、ニューヨークのジュリアード音楽院(リヒャルト)、マンハッタン音楽院(英子)でさらに研鑽を積む。ヨーロッパ各地、アメリカ合衆国、中国、東南アジア等で演奏活動を行う。作曲家フランツ・リストをライフワークと
して1987年リスト協会スイス・日本を設立。CDリリースも数多い。同志社女子大学音楽科講師を45年間務め、今春退職。リスト協会スイス・日本会長。

ダニエル・フォルロー
マルチスタイルの作曲家、編曲家、鍵盤楽器奏者。
チェコ共和国イフラヴァ生まれ。ブルノ音楽院でピアノ、フルート、パイプオルガン、音楽理論、作曲を学ぶ。
ヤナーチェク音楽アカデミー(JAMU)では作曲理論を専攻し、博士課程修了。
これまでに作曲した数千作品には、独奏曲、室内楽曲、声楽曲、管弦楽曲、電子音楽、コンピューター音楽、即興作品、微分音音楽、ポップ/ロック/ジャズ/フュージョン/民族音楽、子どものための歌や600曲以上の様々なジャンルの歌、ラジオ、テレビ、映画、ビデオ、スポーツ、バレエのための音楽や舞台音楽などを含む。
マルチ鍵盤楽器奏者としては、これまでに数千回のコンサートを行う。チェコのロックグループ「Progres 2」と「Bronz」でキーボードを演奏したほか、ソロでは「Forrotronics」として電子楽器を演奏。
ヤナーチェク音楽アカデミー (JAMU)の助教授としてコンピューターや電子音楽を担当し、国際夏季音楽講習で即興と電子音楽を指導した。
自身のレコーディングスタジオで編曲家、サウンドデザイナー、スタジオプロデューサーとしても活動する。
ジュゼッペ・マリオッティ
「伝統と革新が融合する、感動的で力強い対話のような演奏」―この表現は、独創的でカリスマ性あふれるマリオッティ氏の芸術の本質を捉えている。
マリオッティ氏の型破りなキャリアは、発見の精神を特徴としており、有名な作品から見過ごされてきた曲に至るまで、深い解釈と綿密な音楽分析を通じて、作品に新たな命を吹き込んでいく。秀逸で繊細な音色感覚と卓越した技巧、そして作品に隠されたニュアンスや感情を見事に表現する能力が、氏の演奏を特別なものにして
いる。
マリオッティ氏はウィーン古典派の解釈において高く評価されており、また歴史的楽器を用いた演奏や現代作品の演奏でも注目を集めている。特に”フォネ”レーベルから発売されたフェルッチョ・ブゾーニのピアノ作品集は好評を博し、傑作はもとより、ほぼ全ての楽曲が録音されており、20世紀ピアノ音楽の重要な記録として国
際的に高い評価を得ている。
14歳でソロ・リサイタルデビューを果たして以降、ヨーロッパ、アメリカ合衆国、ロシア、イスラエル、そして日本・韓国・台湾・シンガポールなどのアジア諸国で世界的に幅広く活躍している。ヨーロッパの有名なコンサートホールから京都の古代寺院に至るまで、氏の演奏は常に聴衆と評論家を魅了し、ORF、RAI、NDR、NHKなどの大手主要放送局からも注目を集めている。
ハロルド・シェーンベルク(『アメリカン・レコード・ガイド』誌)、ヴィルヘルム・シンコヴィッツ(『ディ・プレッセ』誌)、ピエロ・ラッタリーノ(『ピアノ・タイム』誌)、リッカルド・リサリティ、ピエロ・ブスカローリなどの著名な音楽評論家から、演奏解釈の深さと技術的熟練度において高い評価を得ている。
1963年に生まれ、早くからその才能を著名音楽家から認められたマリオッティ氏は、イタリアのピアチェンツァにある名門「G・ニコリーニ音楽院」でピアノ、オルガン、作曲を学んだ。1982年から1989年にかけてはウィーン国立音楽大学のコンサート科ハンス・グラーフ教授のもとで研鑽を積み、またゲオルク・エーベルト教授のもとでは室内楽のディプロマを取得した。1987年にウィーン楽友協会でデビューを果たし、その演奏は評論家と聴衆の双方から絶賛を博し、国際的音楽活動へと躍進した。
1995年から2003年まで、ウィーンのミノリーテン教会で音楽監督を務め、アントニオ・サリエリの後継者としての役割を果たした。氏はこの伝統に敬意を表し、室内楽オーケストラ「アンサンブル・サリエリ・ウィーン」を設立し、バロック時代の忘れ去られた名曲の数々を100公演以上にわたり21世紀に蘇らせた。
2003年、ウィーン国立音楽大学の委託を受け、徳島文理大学音楽学部のピアノ科教授に就任。2007年には同学部の正教授および学部長に任命され、現在に至る。長きにわたり、日本の音楽教育の発展と、ヨーロッパとアジア間における音楽伝統の国際交流の促進に尽力している。
2008年から2010年まで神戸女学院大学音楽学部の客員教授を務め、2009年からはウィーン国立音楽大学で行われているウィーン音楽セミナー夏期講習会の常任講師を務めている。数々の国際コンクールの審査員も務めるほか、ヤマハ・ミュージック・ジャパン発行の「ピアノの本」では数年にわたり月間コラムを執筆し、音楽専門知識をより多くの読者へと伝えている。
ジュゼッペ・マリオッティ氏は1995年より、ベーゼンドルファー・アーティストの称号を持つ。

青山 佳奈美
札幌大谷短大卒。
青山佳奈美ピアノ教室主催。花明かりコンサートの会代表。
ピティナ•ピアノコンペティション、毎日こどもピアノコンクール、クラシック音楽コンクール、ほっかいどうミュージックフェスティバル、ブルグミュラーコンクールなどの審査員とピティナ•ピアノステップのアドバイザーを務める。
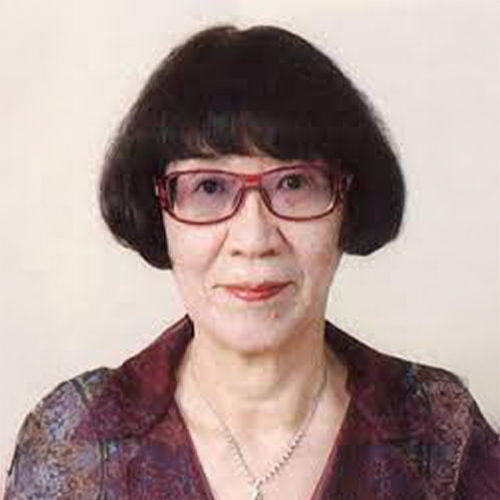
秋葉 暁子
愛媛大学教育学部音楽課程卒業。
ショパン国際ピアノコンクールインアジア組織委員。

秋田 悠一郎
4歳からヤマハ音楽教室にてピアノを始める。
ヤマハ専門コースにて演奏、作曲、アナリーゼ、ソルフェージュ、アンサンブルなどを学び、東京藝術大学音楽学部器楽科ピアノ專攻を経て現在に至る。
PTNAピアノコンペティションやショパンコンクールinASIAをはじめ、国内外での多数のコンクールで受賞。
第1回EIPIC特級部門にて第1位ならびにグランプリ受賞。褒賞にてポーランド/ワジェンキ公園でのショパンコンサートに出演。
2020年にはベートーヴェン生誕250周年バースデーコンサートを開催、交響曲第1番、第3番の連弾編を演奏。以後、毎年ベートーヴェン生誕コンサートを開催している。東京ではベートーヴェンサークルを開催し、2024年4月までに交響曲(連弾編)全曲を演奏。今後ベートーヴェンピアノ作品全曲コンサートを予定している。
ソロリサイタルピアニストとしての他、室内楽や器楽、声楽との共演、また伴奏ピアニストとしても活動。
後進の育成のためレッスン、マスタークラス、講座、コンクールの審査などにも力を入れている。
2018-2019クルーズトレイン「ななつ星in九州」公式ピアニスト。
特にトークコンサートが年齢層問わず好評である。

東 誠三
東京音楽大学卒業後、フランス政府給費留学生としてパリ国立高等音楽院に留学。第52回日本音楽コンクール第1 位をはじめ、数多くの国際コンクールにて優勝・入賞。第24回ショパン協会賞受賞。国内外での活発な演奏活動と共に、東京藝術大学教授、東京音楽大学特任教授として後進の指導を行う。2024年9月より、公益社団法人才能教育研究会会長に就任。近年では日本音楽コンクール、ジュネーヴ国際音楽コンクールなど、数々のコンクールの審査員も務める。日本ショパン協会理事。

安倍 美穂
大阪音楽大学卒業、同大学院ピアノ科修了。ピアノ指導、演奏、創作、と幅広い分野で活動。ソロ演奏のほか、オペラ公演やオペラ講座のアシスタントピアニスト、アンサンブルピアニストのステージも多く務める。こどもたちに向けてのピティナステップトークコンサートを全国各地で展開。作曲家としては、こどものためのピアノ曲集「なにしてあそぶ?」(カワイ出版)「発表会に長くてかっこいい曲を弾こうシリーズ」(ミュッセ刊)カワイこどもピアノコンクール用作品等出版作品多数。ピアノ専門誌「ムジカ・ノーヴァ」にポピュラーアレンジ作品を連載、ミュージカル音楽創作、演奏など、クラシック以外での活動も多い。
ピティナ新曲課題曲賞受賞5回。
伊藤 順一
4歳よりピアノを始め、東京藝術大学附属高校を経て同大学在学中に渡仏し、パリ・エコールノルマル音楽院へ留学。 コンサーティストディプロムをピアノ、室内楽共に首席で修了。その後パリ国立音楽院、リヨン国立音楽院で研鑽を積み、ヨーロッパ各地の国際コンクールに入賞。クロアチア放送交響楽団などと共演。
2019年第4回日本ショパンコンクール第1位。2020年度第47回日本ショパン協会賞受賞。2021年第18回ショパン国際コンクール本大会出場。
デビューアルバム「プロフォンド」はレコード芸術誌「特選盤」に選出され、フランス作品のみを収録したセカンドアルバム「レスポワール」と共に好評を得ている。
現在、神戸女学院大学講師を務める傍ら、首都圏や関西圏を中心に演奏活動を展開している。

伊藤 曜子
第40回フランス音楽コンクール第1位、フランス大使賞、毎日放送賞受賞、第10回ヨーロッパ国際ピアノコンクール金賞グランプリ、第4回フランスピアノコンクール成人の部最優秀賞、第21回日本ピアノコンクール特級の部第1位、2007年度現代フランス音楽賞、2008,09年度メシアン「鳥のカタログ」特別賞。 2014,15,16,18年に東京文化会館小ホールにてリサイタルを開催、CD「Favori」「POULENC Les soirées de Nazells」をリリース。東邦音楽大学大学院修了。日本大学豊山女子高等学校中学校芸術科講師。フランス音楽コンクール審査員。藤井一興氏、神野明氏、山田忍氏に師事。日本演奏連盟会員。全日本ピアノ指導者協会正会員。

稲原 桂子
熊本音楽短期大学卒業
ウィーンマスターコース受講、Diplom取得
杉谷昭子先生に25年に亘り師事
全日本ピアノ指導者協会(PTNA)正会員
PTNAうきうきステーション代表

岩佐 生恵
PTNA評議員、PTNA今治支部長、ショパン国際コンクールinASIA審査員。
ブルグミュラーコンクール愛媛2地区実行委員長。
さくらピアノコンクール愛媛地区大会実行委員長。
神戸女学院大学音楽部卒

岡村 重信
桐朋学園大学音楽学部卒業 南カリフォルニア大学音楽学部修士課程修了
1985年より鹿児島国際大学国際文化学部音楽学科教授(現在に至る)
1996~97年ロンドン大学キングスカレッジ研究員
ロンドンアレキサンダースタジオでアンソニー・キングスリーに師事
米国クラーク大学にて交換教授
16歳からソロ演奏活動を続けるとともに、国内の主なコンクールで審査員
プロを目指すピアノ学習者とアマチュア学習者を分けた教育法を実施
アマチュアのためのポピュラー音楽を含んだピアノ奏法講座実施
「異文化コミュニケーション」「演奏家と鑑賞者とのコミュニケーション」
「大学に於ける音楽教育」等の著書(大学教育出版社)

尾形 牧子
武蔵野音楽大学卒業、日本ショパン協会正会員・東北支部長、(公財)日本ピアノ教育連盟東北支部長、宮城県芸術協会会員、仙台国際音楽コンクール企画推進委員
小川 典子
リーズ国際ピアノコンクール入賞以来30年以上、英国と日本を拠点に世界の主要オーケストラ・指揮者との共演や、室内楽、リサイタル等で世界各国へ演奏旅行を行う他、国際的なコンクールでの審査、各国でのマスタークラスなど、国際的で多彩な活動を展開中。
録音は、BISより35枚目のCD「サティ:ピアノ独奏曲全曲集Vol.“ヴェクサシオン”」、新譜リチャード・ドゥヴニオン「クラヴィレリアーナ」世界初録音発売中。
2013、14年にはBBCプロムスへ連続出演。その後ポーランド放送響、モスクワ放送響、サンクトペテルブルグ響、BBC響など英国ツアーのソリストとして共演。またイギリス、フランス、ドイツ、ポーランド、韓国を始め数々の音楽祭にも招聘され、リサイタルやマスタークラスを行う。
リーズ国際、グリーグ国際、クリーブランド国際コンクール審査員。浜松国際ピアノアカデミー音楽監督。浜松国際ピアノコンクール審査委員長。国際音楽コンクール世界連盟役員。英国ギルドホール音楽院教授。東京音楽大学特任教授。ミューザ川崎シンフォニーホールアドバイザー。ジェイミーのコンサート主宰。NAS英国自閉症協会文化大使、イプスウィッチ管弦楽協会名誉パトロン。
文化庁芸術選奨文部大臣新人賞受賞、川崎市文化賞受賞。
2017年11月にはこれまでの貢献をたたえて英国ギルドホール音楽院より「フェロー」の称号が授与された。
著書「夢はピアノとともに」。訳書「静けさの中から」。
パンデミック禍も世界中の学生へ語りかけ、オンラインコンサート開催など精力的に行なっている。
尾見 林太郎
ドイツ国立シュトゥットガルト音楽演劇大学大学院ピアノ専攻科及びドイツ歌曲伴奏クラス修了。
13年に渡るドイツ生活から帰国後、演奏活動と後進育成、ピアノ指導者のためのセミナー等に精力的に取り組んでいる。
見た目のイメージそのままのスケールの大きい演奏解釈と色彩感豊かな音色変化、見た目に反する美しく繊細な弱音が持ち味。これまで2枚のCDをリリース。
ヨーロッパ国際コンクール、ピティナコンペティション、バッハコンクール、ブルグミュラーコンクール等で審査員を、石川音楽事務所主催さくら、あおい、DOLCEコンクールでは審査員長を務めている。
門下生にコンクー優勝者、入賞者を多数輩出。
これまでに田邊融、渡邊規久雄、エルジェーベト・トゥーシャ、アマデウス・ウェーバージンケ、コンラート、リヒター、タマーシュ・ヴァーシャーリの各氏に師事。

垣内 敦
桐朋学園高校音楽科を経て、桐朋学園大学音楽学部を卒業。
その後、ドイツのライプツィヒ音楽大学および大学院を卒業。
1997 年にフランツ・リスト国際ピアノコンクール(ワイマール)にてファイナリストとしてディプロムを、1998 年には第 44 回マリア・カナルス国際音楽コンクール(バルセロナ)にて特別メダルを受賞。ドイツ各地でソロリサイタル、室内楽ならびにオーケストラとの共演等の活動を行う。帰国後、王子ホール、東京文化会館、津田ホールにて6回にわたり東京での自主リサイタルを開催のほか、イタリアでの「ローマの夏音楽祭」への出演、フルートのアンドレアス・ブラウ氏、デニス・ブリアコフ氏、チェロのフランツ・バルトロメイ氏、トロンボーンのユルゲン・ファン・ライエン氏など内外の著名な音楽家の共演者としても信頼を置かれるなど、ソロ・室内楽両分野において国内外で精力的に演奏活動を行っている。
2024 年にはエリザベト音楽大学創立75周年記念演奏会シリーズにて広島交響楽団とチャイコフスキーの協奏曲第 1 番を演奏。
また全日本学生音楽コンクールやピティナピアノコンペティション、JPTAピアノオーディション、ありあけジュニアピアノコンクール、中国ユース音楽コンクール他、多くのコンクール審査も務める。現在、エリザベト音楽大学教授。

京谷 光真
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、東京藝術大学を卒業後渡欧。2024年ブリュッセル王立音楽院修士課程を最高栄誉賞付きで修了。
3歳よりヤマハ音楽教室、マスタークラス演奏研究コース修了。
自作曲で2007、2008、2011年JOCハイライトコンサート、2009年シティコンサート出演。
2010〜2013年Concert VIVACE出演。
第25回彩の国埼玉ピアノコンクールE部門金賞及び埼玉新聞社賞。
第1回ひのっこピアノコンクール第3位。
カワイ表参道コンサートサロンパウゼにてランチタイムコンサート出演。Bösendorfer Tokyoにてアフタヌーンコンサート出演。
2016、2018年ラ・フォル・ジュルネ出演。
これまでにピアノを及川良子、北島公彦、秦はるひ、渚智佳、佐藤俊、後藤康孝、迫昭嘉、坂井千春、Johan Schmidt、菊地洋子各氏に師事。作曲を大政直人氏に師事。
Henri Barda、Mikhail Voskresensky、Yves Henry、Anne Queffélec各氏のマスタークラスを受講。現在、演奏活動の傍ら、伴奏や編曲も精力的にしている。

坂井 千春
東京藝術大学音楽学部附属音楽高校、同大学ピアノ科を経て同大学院修士課程修了。ロータリー奨学金により渡欧。ブリュッセル王立音楽院とパリ・エコール・ノルマルでコンサーティスト・ディプロムを取得。マリア・カナルス、ポルト、ロンドン国際コンクール優勝、ロン・ティボー国際コンクール、エリザベート国際コンクール入選などの数多くの国際コンクールで入賞し、ロイヤル・フェスティバル・ホールでフィルハーモニア管弦楽団と共演など、欧米と日本各地でコンサートを行なった。
第2回出光音楽賞受賞。第16回青山バロックザール賞受賞。
現在、東京藝術大学ピアノ科教授、名古屋音楽大学客員教授として後進の指導にあたり、各地のコンクール審査員やマスタークラスも務めている。また、近年は女性作曲家の研究を行い、女性作曲家作品のみのリサイタルや、シャミナードの作品集CD制作、シャミナードのコンチェルトシュトゥックの日本初演など、積極的に女性作曲家の作品紹介を行なっている。

城 寿昭
東京藝術大学音楽学部卒業。ブリュッセル王立音楽院卒業。 名古屋音楽大学非常勤講師。

角野 美智子
桐朋学園大学ピアノ科卒業後、米国ニューイングランド音楽大学大学院に留学。主宰のSumino Piano Academyより、各種コンクールで延べ100名以上の受賞者を輩出。また、東京藝大、藝高をはじめ、音大・音高受験実績でも高い実績を上げる。ピティナ指導者賞連続25回、特別指導者賞14回受賞。導入期から上級までバランス良く育て上げる指導法で高い評価を受ける。指導法や子育てに関する講演「感性を磨く真に音楽好きな生徒を育てるには」「原石を磨く指導法」「ワンランク上の指導法クリニック」を全国各地で開催。一般社団法人全日本ピアノ指導者協会(ピティナ)正会員および全国大会審査員、ショパン国際ピアノコンクールinAsia組織委員および全国大会・アジア大会審査員、日本バッハコンクール千葉実行委員長および全国大会審査員をはじめ、多数のコンクール審査員を務める。著書に『「好き」が「才能」を飛躍させる子どもの伸ばし方』(ヤマハミュージックエンタテイメントホールディングス)。

田代 美佳
フェリス女学院大学音楽学部器楽科卒業、同大学大学院音楽研究科修了。その後クロアチアにて研鑽を積む。大学在学中に神奈川フィルハーモニー管弦楽団、ポーランドクラクフ管弦楽団と共演。受賞歴として、マッサフラ国際音楽コンクール(イタリア)ピアノ部門第1位、バルレッタ国際音楽コンクール(イタリア)ピアノ部門第2位など。門下生が、ショパン国際ピアノコンクールin ASIA 金賞、ピティナ全国大会金賞、ヨーロッパ国際コンクール
inJAPAN 金賞他多数受賞。ピティナ特別指導者賞、ショパン国際ピアノコンクールin ASIA指導者賞、ヨーロッパ国際ピアノコンクールinJAPAN最優秀指導者賞受賞。全日本ピアノ指導者協会正会員、IMC Music
PublisherJapanショパン国際ピアノコンクールin ASIA 組織委員、ピアノ教育連盟会員、元岩手県文化芸術振興審議会委員、ブルグミュラーコンクール岩手地区代表。

大楽 勝美
東京藝術大学附属音楽高等学校、東京藝術大学卒業、同大学院修了。同大学指揮科助手を務めた後、イタリアアカデミアサンタチェチーリア音楽院に給費留学。
第3回ヴィオッティヴァルセジア国際ピアノコンクール第1位
第21回エンナ国際音楽コンクール第2位
札幌大谷短期大学(現札幌大谷大学)助教授、北海道教育大学講師を務めた後、2002年音楽工房G.M.Pを設立。
ヨーロッパ国際ピアノコンクール特別優秀指導者賞。

棚橋 妙子
桐朋学園大学音楽学部演奏学科ピアノ専攻卒業。在学中は故三宅洋一郎氏に師事。卒業後、札幌新人演奏会に出演。岩見沢、札幌、横浜、東京等にてリサイタルおよびデュオリサイタルを行う他、桐朋会コンサート、Klavier Abent、各種コンサートに出演。スロバキアとハンブルグの音楽マスタークラスに参加し、ウクライナ・キエフでの第2回ホロヴィッツ青少年国際ピアノコンクールにおいて指導者賞受賞。日本ピアノ教育連盟北海道支部、北海道桐朋会、日本ショパン協会北海道支部、全日本ピアノ指導者協会、日本ピアノ教育連盟オーディション、全日本学生音楽コンクール、毎日こどもピアノコンクール、カワイ音楽コンクール等の審査と公開講座の講師も務める。桐朋学園大学音楽学部演奏学科ピアノ専攻卒業。現在、札幌大谷高等学校音楽科非常勤講師。カワイピアノセミナー担当講師。

鳥越 未加緒
熊本音楽短期大学(現平成音楽大学)卒業。同専攻科修了。
下関短期大学講師。
全日本ピアノ指導者協会正会員。
ピティナピアノコンペティション審査員。
ピティナピアノステップアドバイザー。
その他九州・山口ジュニアピアノコンクール等の審査員を務める。
永井 礼子
桐朋学園大学ピアノ科卒業。桐朋学園大学卒業演奏会、兵庫県新人演奏会に出演。
ウィーン国立アカデミア夏季セミナーに参加。E・ムラチェック教授に師事。「今後の活躍が楽しみなピアニスト」に出演。新日本フィルハーモニー、ヴィエールフィル(現在の大阪センチュリー交響楽団)、東京シティフィル、東京アマデウス管弦楽団と協演姉妹による神戸市主催「風見鶏コンサート」アメリカンセンター主催によるデュオ・コンサート等、毎年、札幌、大阪、神戸にて開催。これまでに故井口基成、北村陽子、故エルンスト・ザイラー、故三善晃の各氏に師事。
現在(社)全日本ピアノ指導者協会正会員
1987年より同協会コンペティション審査員。
ピティナ指導者賞、特別指導者賞、日本クラシック音楽コンクール優秀指導者賞
ショパン国際コンクール・イン・アジア指導者賞を受賞。

中川 朋子
ザルツブルク芸術大学”モーツァルテウム”修士課程修了。桐朋学園大学音楽学部非常勤講師、名古屋音楽大学教授。

西川 奈緒美
大阪音楽大学付属音楽幼稚園、音楽学園(現 音楽学院)小、中、高校過程を経て大阪音楽大学音楽学部ピアノ専攻卒業 株式会社おとぷちミュージックラボ代表。
ショパンコンクールinアジア組織委員 全日本ピアノ指導者協会正会員 全日本ピアノコンクール副委員長
ショパン国際ピアノコンクールinアジア指導者賞、ピティナ指導者賞24回受賞、トヨタ指導者賞、特別指導者賞2回、ヨーロッパ国際ピアノコンクール特別指導者賞など受賞。
ショパンコンクールinアジア、ピティナピアノコンペティション、ヨーロッパ国際ピアノコンクール、全日本ピアノコンクール等審査員
主宰のおとぷちピアノ教室では、オリジナル教材「五巻シートレッスン®️」が人気を博し、全国でも指導者が活用。幼児の感性を磨く指導法、「しあわせピアノ塾®️ルボヌール」で生徒の才能を伸ばすレッスン法、演奏法勉強会、幸せになる教室運営法などの講座を開催。ブルガリアソフィア国立管弦楽団と共演する門下生のピアノコンチェルトコンサートを2017年、2019年と開催し好評を博す。

根津 栄子
武蔵野音楽大学卒業。
ピティナ特別指導者賞、優秀指導者賞、カワイ音楽コンクール最優秀指導者賞、ショパン国際コンクールinアジア指導者賞、ちば音楽コンクール優秀指導者賞を受賞。ヨーロッパ国際コンクールinJapan優秀指導者賞を受賞。
現在、一般社団法人全日本ピアノ指導者協会正会員、指導者育成委員、市川フレンド・ステーション代表、ちば市川バスティン研究会代表。ピティナ・ピアノコンペティション全国決勝大会審査員、ショパン国際コンクールinアジアアジア大会審査員。全国各地での指導法講座や、音楽雑誌執筆でも活躍中。小さなピアニストのための必須アイテム、 フィットペダル&ボード考案。著書:『こどものスケール・アルペジオ』(音友) 『プレ・こどものスケール・アルペジオ』(音友) チェルニー30番~小さな30の物語 上下巻(東音企画)
2020年4月から2022年3月まで音楽雑誌ムジカノーヴァ(音友)に『生徒を変身させる24のキーワード』を連載。
続いて2022年9月から『生徒を変身させる24のキーワード』からテクニック編を使いブルクミュラー25の練習曲指導法を2024年9月まで連載。

秦 江里奈
桐朋女子高等学校音楽科を経て桐朋学園大学を卒業。
蓼科高原音楽祭奨励賞。やちよ音楽コンクールにて第3位、及び審査委員長賞受賞。
第1回レナードバーンスタインにとっての最初で最後のパシフィックミュージックフェスティバルに参加。トーマスハンプソンのリサイタルにてマイケルティルソントーマス指揮によるマーラーの「さすらう若人の歌」のピアノパートを受け持つ。その他ロンドン交響楽団員とのアンサンブルで多数出演。サントリー大ホールにてPMFオーケストラ公演のチェレスタを担当する。
八ヶ岳音楽セミナーにて最優秀賞を受賞。
桐朋学園弦楽器伴奏研究員、洗足学園音楽大学ピアノ演奏研究所を修了の後フランスへ留学。
パリ・エコール・ノルマル音楽院にて最高課程演奏家ディプロム(コンサーティスト)をピアノで満場一致、同ディプロムの室内楽部門を満場一致の首席にて取得。
ザルツブルク音楽祭夏期講習にて選抜アカデミーコンサートに毎回出演。
アルベール・ルーセル国際ピアノコンクールにて最優秀室内楽賞。
パリ・サルコルトーにてリサイタル。
マリア・カナルス国際コンクールで1位なしの第2位と、併せて特別賞メダルを受賞。
日本演奏連盟主催で東京文化会館にてリサイタルを開催。
チャイコフスキー国際コンクールにてセミファイナリスト。パリ・ショパン協会主催、ショパンフェスティバルに出演、その模様をフランス第5チャンネル及びケーブルテレビMezzoに放映される。
ゴスタシュバルツ・インターナショナルアーティスト事務所に専属契約、アレキサンドル・デュマ劇場の年間シリーズ公演にて「フランス音楽と日本音楽」のリサイタルに出演。エコールノルマルにてムニエクラスのアシスタントを務めるが2001年に帰国。川崎市よりアゼリア輝賞受賞。
今までに宗施月子、北村陽子、伊達純、アンリエット・ピュイグ=ロジェ、ジェルメーヌ・ムニエに師事。全日本ピアノ指導者協会正会員、洗足学園音楽大学(ピアノコース)講師、桐朋学園大学(心身コントロール)講師。

平間 百合子
東京都出身。3歳より松田晴造、文代夫妻に音楽教育を受け国立音楽大学附属小学校、中学、高校、同大ピアノ科を経て渡欧米。オーディション合格者による国立音楽大学ソロ・室内楽コンサート、東京にて期待される音楽家の夕べ等に出演。仙台フィル、仙台ニューフィル、ガブリエリブラス、イタリアジーノ・ネリやチルコロマンドニスティコフローラ他とコンチェルトを協演。リサイタルや土曜サロンコンサート等を多数主催。芸術祭音楽会、日本歌曲の夕べ、歌い継がれゆく日本の歌、フランス音楽の夕べ、ドイツリートの夕べ、モーツァルト協奏曲連続演奏会、ミューズの夢コンサート、等のシリーズでフルート・ヴァイオリン・マリンバ・クラリネット・声楽家と多数競演。ヨーロッパ国際ピアノコンクール、ショパン国際ピアノコンクール全国決勝大会、アジア大会、アメリカシンシナティワールドピアノコンクール等の審査員を務め、ピティナセミナー、公開レッスンの依頼を釧路、北見、青森、盛岡、山形、東京、神奈川、千葉、静岡、大阪、広島、沖縄などで実施。トークコンサートを千葉、伊賀、静岡、福井、大阪、宝塚、九州、宮古島等から依頼を受け演奏。ピティナ特別指導者賞、トヨタ指導者賞、ヨーロッパ国際ピアノコンクールinJAPAN特別優秀指導者賞、ショパン国際ピアノコンクールinASIA特別指導者賞、全日本ピアノコンクール指導者賞、神奈川コンクール指導者賞、カナダoutstanding teacher、宮城県芸術協会功労賞などを受賞。現在、金の星ピアノ研究会主宰、常盤木学園高校音楽科講師、(公社)宮城県芸術協会会員、(公財)日本ピアノ教育連盟会員、(社)全日本ピアノ指導者協会正会員、ショパン国際ピアノコンクールinASIA組織委員会委員、(公社)日本演奏連盟会員

松嶋 知香
一般財団法人杉谷昭子ピアノアカデミー代表理事。杉谷昭子氏にピアノを学び、大阪芸術大学で作曲を学ぶ。SUMMER MUSIC ACADEMY BERN (スイス)マスタークラス講師。

圓山 さちこ
4歳よりピアノをはじめ、ピティナピアノコンクール等国内コンクール多数入賞。2011年札幌にてピアノソロリサイタル開催。
また知床にて静岡交響楽団コンサートマスターらと二夜連続コンサートにて共演や、札幌市主催時計台まつりコンサート、MFO長万部音楽祭選抜ファイナルコンサート(ソロ・室内楽)等数々のコンサートに出演。PMF教育セミナー受講。
2015年日本ピアノ研究会より最優秀指導者に認定される。第7回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin japan特別優秀指導者賞受賞。
ピティナ新人指導者賞受賞。ヨーロッパ国際ピアノコンクールin japan 優秀指導者賞受賞。
これまでにピティナピアノコンクール全国大会出場、ヨーロッパ国際ピアノコンクールin japan全国大会にて銀賞、銅賞、ディプロマ賞、ブルグミュラーピアノコンクール、グレンツェンピアノコンクール金賞等多数輩出。
全日本指導者協会会員。ハイメス・アーティスト会員。 日本音楽クラシックコンクール、ヨーロッパ国際ピアノコンクールin japan審査員。
日本こども教育センターリトミック認定講師。札幌大谷短期大学音楽科卒業。同短期大学音楽専攻科修了。学士(芸術学)取得。札幌サクラボミュージック主催。株式会社ミュージックパレット代表取締役。 國學院大学北海道短期大学部幼児・児童教育学科特別講義講師。

山内 鈴子
神戸女学院大学音楽学部卒、洗足学園大学音楽学部マスターコース修了。
東京読売新人演奏会出演、朝比奈隆指揮大阪フィルハーモニー交響楽団との 協演にてデビュー。佐渡裕指揮エウフォニカ管弦楽団、関西フィル、京都市 交響楽団ほか、関西の主要オーケストラと20数回協演している。また、ソロリサイタル、室内楽の演奏会も多数出演している。また、中国の蘇州人民会堂こけら落し演奏会に出演、ウクライナフィル(キエフ)、ソフィアフィル (ブルガリア)と現地で協演。ウィーン・プライナー音楽院と神戸女学院との交流コンサートを10数年にわたり開催している。
故東貞一、故EFザイラー、奥村智美、故M.エッガー各氏に、ウィーンにて A.イエンナー、故ザイドルホーファー各教授に師事。
第17回音楽クリティッククラブ新人賞、神戸灘ライオンズクラブ音楽賞、 第9回ブルーメール賞を受賞、宝塚市文化功労者表彰を受ける。
現在、神戸女学院大学講師、元大阪芸術大学講師。日本演奏連盟、宝塚演奏家連盟(元会長)、日本ピアノ教育者連盟、リスト協会各会員、元宝塚市文化財団評議員。多くのピアノコンクール審査委員長、審査員を務めており、指導者賞を数多く受賞している。また、2024年8月ウィーンにて開催された「第13回ロザリオ・マルシアーノ国際ピアノコンクール」の審査員を務めた。

油井 美加子
大阪音楽大学卒業、同大学院修了。
関西新人演奏会に出演。
91、95、98、00、02、05、07、09、11、13、15、17、19、23年にリサイタルを開催する他、大阪センチュリー交響楽団、大阪シンフォニカー交響楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団、ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団、テレマン室内管弦楽団、モーツァルト室内管弦楽団等と協演。
また、デュオリサイタルや室内楽、サロン・コンサート、リサイタルの伴奏等、多方面で活躍する他、 NHK‐FMリサイタル、FM大阪等にも出演。
パリ・エコール・ノルマル音楽院にて、ジェルメーヌ・ムニエ氏のもとで研鑽を積み、満場一致にてDiplôme Supérieur を取得。パリにてリサイタルを開催。
山田みつ、金澤希伊子、松浦豊明、安川加壽子の各氏に師事。現在、大阪音楽大学教授。
日本ショパン協会関西支部、日本ピアノ教育連盟、宝塚演奏家連盟各会員。

若林 顕
日本を代表するヴィルトゥオーゾ・ピアニスト。
東京藝術大学、ザルツブルク・モーツァルテウム、ベルリン芸術大学で研鑽を積む。20歳でブゾーニ国際ピアノ・コンクール第2位、22歳でエリーザベト王妃国際コンクール第2位の快挙を果たし、一躍脚光を浴びた。
その後ニューヨーク・カーネギーホール(ワイル・リサイタル・ホール)で鮮烈なリサイタル・デビューを飾り、N響やベルリン響、サンクトペテルブルク響といった国内外の名門オーケストラやロジェストヴェンスキーら巨匠との共演、国内外での室内楽やソロ・リサイタル等、現在に至るまで常に第一線で活躍し続けている。リリースした多くのCDがレコード芸術・特選盤となり、極めて高い評価を受け続けている。
2014年、2016年にサントリーホール(大ホール)、2020年に東京芸術劇場コンサートホールでソロ・リサイタルを行い、2023年からは同ホールでリサイタル・シリーズを開始し、大成功をおさめている。
また、自身では3回目となる「ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全曲シリーズ」を2017年に完結し、2018年より2022年まで「ショパン:ピアノ作品全曲シリーズ」を行った。第3回出光音楽賞、第10回モービル音楽賞奨励賞、第6回ホテルオークラ賞受賞。